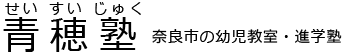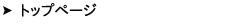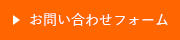■ 幼児(2・3歳児)を受付中です。
幼児教室の特徴
青穂塾幼児教室は、幼・小・中一貫教育です。
青穂塾幼児教室の教育は、幼児・小学生・中学生と切れ目なく続いているため、10年前後在籍する生徒が多くいます。 そのなかで青穂塾幼児教室の教育がその生徒にどんな効果を与えているのか検証し、青穂塾幼児教室の授業を絶えず改良しています。
青穂塾幼児教室は分析力、思考力、発想力のある若者を育てることを目標にしています。
青穂塾幼児教室は、ただ単に合格さえすればいい、成績が上がりさえすればいいという考え方の塾ではありません。 社会に出て社会のために貢献できる若者を育てるのが使命だと考えています。
青穂塾幼児教室は個人の能力に合わせます。
青穂塾幼児教室は1対1の個人指導ではありませんが、個人差の出やすい部分は、個人の能力に合わせて進みます。
青穂塾幼児教室はテレビゲームを禁止しています。

幼児教室の授業
★ 絵本を楽しむ心、国語の力(2学年上の実力)
幼児期は国語力が飛躍的に発達する時期です。 質の高いお話を読み聞かせる事により、親子の精神的な絆を強めるだけでなく、子どもたちの豊かな感受性、表現力、想像力を育み、小学生低学年の基礎を作ります。 青穂塾幼児教室では精選された絵本を使って、絵本を楽しむ心を育て、国語力の発達に結び付ける指導をしています。
★ 分析する力、考える力、創造する力(レベルの高い実験・工作を楽しむ)
幼児の場合いろいろな物を組み立てたり、分解したり、試行錯誤することによって分析力、思考力が発達します。 この試行錯誤が大切です。青穂塾幼児教室では、いろいろな作業・実験をしながら試行錯誤を大切にする指導をしています。
★ 子どもをテレビゲームから守ろう!(テレビゲームに頼らない生活習慣)
テレビゲームに熱中する幼児は、集中力が持続しない傾向があります。 また、バーチャル(仮想現実)の世界に飲み込まれてしまうと、現実の世界にうまく対応できなくなる可能性があります。そのため青穂塾幼児教室では、テレビゲーム類を禁止しています。
青穂塾幼児教室でもこの問題に真剣に取り組んでいます。
★ 自然を見る目、社会を見る目(仮想現実に飲み込まれないために)
幼児期の子どもにとって大切な事は、本物を見せる事です。その為に青穂塾幼児教室では教室の外に積極的に出ています。 毎日の生活で見逃している植物や昆虫の観察の他、採取した生物の飼育・観察指導などもしています。

★ ひらがな・カタカナよりも指の動き(指先が大脳を鍛える)
青穂塾幼児教室ではひらがな・カタカナを覚える事に必死なるのでなく、大人になって指の動きが悪く、くせ字、悪筆で悩まないように鉛筆を持てること、指を動かすことに力を入れています。
★ 個別指導で低料金(一人一人を確実に)
青穂塾幼児教室は、幼児の行動のすみずみまで目を行き届かせる、個別指導です。
幼児教室のモットー
あなたのお子様が通われている幼児教室は大丈夫ですか?
「天才児を目指す」だの「○○教育」だのすばらしい言葉が並んでいます。ところが以前から当塾のパンフレットに書いてきたのですが、幼児教室出身者はそうでない子供たちよりも問題を抱えていることが多いのです。
たとえば週刊文春2008年9月18日号でも記事になっていますが、自塾の出身者を追跡調査して問題ありと認め規模を縮小した比較的良心的なところもあるのに対し、問題児を世に送り続けているところもあります。
その幼児教室については内部告発が出ているという風聞を私も何回か耳にしたことがありますが、やはり事実なのでしょうか。
幼児教室出身者にはどういう問題があるのでしょうか?
簡単に言えば、知識主義・暗記主義に陥っているのです。もっとひどい言い方をすれば、分析能力・論理性が育っていない(というより破壊されている)ように私にはみえます。分析能力や論理性を高める教材を利用しているはずなのですが、とても効果が出ているような気がしません。小学校低学年ではとても優秀に見えるのですが、それは恐らく先取り学習によるものと思われます。やがて高学年になってくると怪しくなってきます。今まで成績が悪いと思っていた子供たちに追い抜かれ始めるのです。中学高校あたりになってくると落ちこぼれ始めます。
逆にこの頃になると、それなりにきちんとした家庭教育を受けた子供、充分に遊びを経験した子供たちが伸び始めるのです。 (週刊文春2008年9月18日号に分かりやすくまとめられています。)
小学校高学年頃になって伸びてくる子供たちにはどんな特徴があるのでしょうか?
「好奇心旺盛でいろいろなことにチャレンジする。」「きちんとした生活習慣をもっている。」「忍耐力、集中力がある。」ような子供たちです。逆に優秀だが挫折し始める子供たちもいます。競争心の強すぎる子供たちです。人に勝つことを目標にするのは無理があります。なぜならオリンピックを見ても分かるように頂点に立てる人はほんの一握りの人だからです。しかもすべての面で頂点に立つことはできません。そのような子供たちは自分が頂点に立てないと悟った時、競争が終わったとき、競争に負けたと感じたとき、すべての努力を放棄してしまいます。
それに対して「好きだから」「興味があるから」やっている子供たちは、どんな逆境でも耐え抜きます。たとえば、好きなことをさせてもらえるのだったら一食抜くぐらい平気なのです。そしていつか栄冠を勝ち取ります。ノーベル賞受賞者にもそんな方がおられますね。勉強は一生続けるもの。それには勉強を好きにならなければなりません。
時々言われることがあります。
青穂塾の授業を見ると「あれなら家でもできそうだ。でもいざ自分でやってみるとできない。」そうです。家ではできそうでできないことを授業でしているのが青穂塾です。
たとえばあなたはオタマジャクシすくいをしたことがありますか?青穂塾の新聞折り込みチラシにオタマジャクシを子供たちがすくっている写真を載せていました。そうするとそれを真似て農家にたいへん怒られた方がいます。田んぼの畦は水をためるために農家では大切に管理しておられます。コンクリートで固めた丈夫な畦もあるのですが、地形上とても不安定な畦もあります。そういうところを踏み荒らすと、農家の方が怒るのです。(実は私も怒られた経験があります。)また最近はカエルも減ってしまって、オタマジャクシのいない田んぼもあります。また田んぼは様々な生物の宝庫でもありますから、田んぼに行けばオタマジャクシすくいで終わってしまってはもったいないのです。 こうして長年の経験を生かした授業で青穂塾は皆様の子育てのお手伝いをしています。(農地では除草剤や農薬の散布もありますので、不注意に近づいてはいけないときがあります。)
先取りはすぐれた方針ではありません。特に幼児期や小学校低学年では危険ですらあります。なぜなら、その時期の行われるのはほとんどが質の悪い教育だからです。家庭で行われるものや、素人判断で行われる多くの先取り教育は幼児の特質をふまえずにするため、暗記中心の反復練習になってしまいます。そのため結果的に分析能力や論理的思考力を破壊することにつながっています。
たとえば幼児に少し高度な算数学習をさせたとしましょう。その幼児にとってその時それほど必要でない学習をさせるのです。小学校に入れば簡単に学習できるけれども、幼児では高度になるような内容です。うまく指導すればその幼児はそれを学習することができます。
ところが幼児の脳はそれほど発達していませんから、その高度な学習以外のことは学習できなくなります。その幼児にとってどうしても学習すべき重要な内容に注意が向かなくなるのです。その結果小学生になれば簡単に学習できるような学習のために、幼児で学習するべき大切な内容を習得する機会を無くしてしまうのです。
もう少し詳しく説明しましょう。
たとえば、AからZまでの発達要素があるとします。ある時はCの要素だけが急激に発達します。その間C以外の要素はほとんど発達しません。やがてCの要素がある程度発達しますとCの要素の発達が止まる時がやってきます。するとCとは全く無関係なSの要素が急激に発達し始めます。この時Sの要素以外はほとんど発達を止めてしまいます。今まで発達していたCの要素も発達しません。そしてSの要素がある程度発達しますとSの要素の発達が止まる時がやってきます。すると次にはCやSとは無関係なYの要素だけが発達し始めます。こうして、予測もつかない要素が次々にバラバラに一つずつ個別に発達していくのです。
このような発達の仕方をアメリカの発達心理学者ゲゼルは「ジグザグの発達」と言ったそうですし、日本の発達心理学者である園原太郎は「横の発達ないしは面としての発達」と言ったそうです。(保育講座・初等教育原理、森上史朗編、ミネルヴァ書房)
このような発達の仕方をする幼児に高度な算数を教え込んだとしましょう。当然それ以外の、幼児にとって重要な要素は発達を止めてしまうのです。 幼児は分析能力や論理的思考力がそれほど発達していませんので、先取り学習は暗記中心の反復練習になってしまい、結果として分析能力や論理的思考力が発達を止めてしまうのです。
人間の耳はたいへん重要な感覚器です。
たとえば目で見た文字はいったん音声信号に変えてから脳で処理します。そのとき目は錯覚を起こしたりしますし、脳は信号処理にたいへん手間取ったりします。だから幼児に自分で文字を読ませると、視覚信号を音声信号にかえる作業だけで精いっぱいになり、脳で内容把握するまでに力が及びません。ところが耳から直接聞くことにより、脳の負担を減らすことが出来、幼児でも知能・語彙・推論などを利用して意味を理解するという作業が出来るようになります。ですから幼児期は必ず読み聞かせをしてあげてください。
ただ注意すべきは読み方です。立て板に水のようにものすごい早さで読み聞かせをなさっているお母さんを図書館で何人か見たことがあります。そのうちのある子供はそれをいやがってお母さんの膝から逃げていってしまいました。これでは逆効果ではないかと思います。やはりゆったりと子供と会話を交えながら読んで欲しいものです。
「耳学問」は本来悪い意味で使われる言葉ですが、幼児にとっては大切な言葉だと青穂塾では考えています。
幼児に考えなさいと言っても考えることはできません。
でも体を動かすと脳が働きます。足を動かす、手を動かす、指先を動かす、目で見つめる、耳をすます、手で触る、体で触れる。それによって脳が働きます。だから幼児には体を使いながら考える場面を設定する必要があります。そういう面で考えると「遊び」の大切さが分かってきます。
テレビ・テレビゲーム・インターネット・・・これらバーチャルリアリティ(仮想現実)では、遊んでいるのではなく遊ばされているだけなので、子供たちは脳の一部しか使っていません。2004年日本小児科医会と日本小児科学会がテレビやDVDの視聴を控えるように警告を出しました。またテレビゲームの危険性も指摘されていますが、これらへの反論も多くあります。でも安全性の確認されていないものを子供に与えるのは間違っていると思いませんか。
「安心・安全」を求めるのは食べ物だけではないと思います。